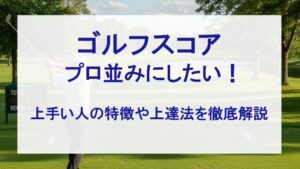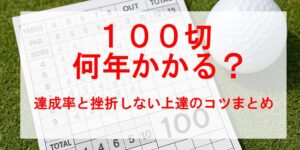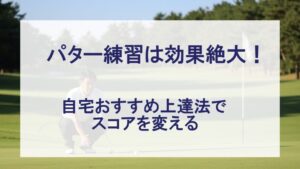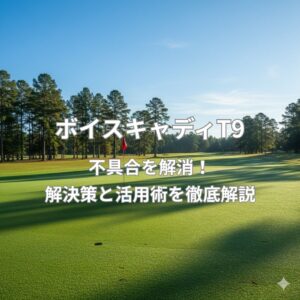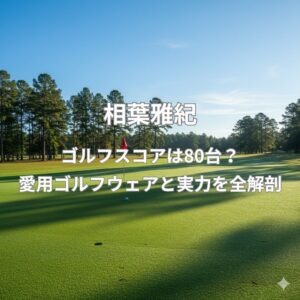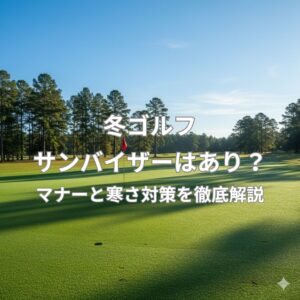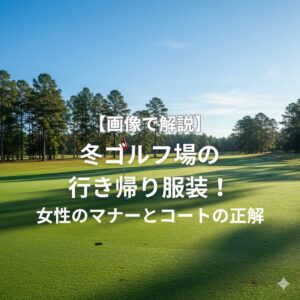ゴルフ中継を見ていると、プロのトーナメントにアマチュア選手が出場し、活躍する姿を目にすることがあります。
「同じ大会に出ているのに、プロとアマチュアはどう違うの?」「アマチュアは賞金をもらえるの?」そんな疑問を感じたことはありませんか?
ゴルフの賞金、特にアマチュア選手が関わる場合のルールは、近年変更もあり少し複雑です。
この記事では、アマチュアとプロの違いの基本から、2022年のルール改定で変わったアマチュア賞金の上限や賞金規定について詳しく解説します。
もしアマチュアが優勝したら賞金はどうなるのか、アマチュア資格の取得方法やアマチュア資格のメリット、アマチュア大会に出るにはどうすればよいか、初心者向けのアマチュア大会の情報、そしてプロになるにはどうすればよいか、アマチュア優勝からのプロ転向ルートまで、あなたの疑問にすべてお答えします。
記事のポイント
- アマチュアとプロゴルファーの根本的な違い
- 2022年改定のアマチュア賞金規定(上限額など)
- アマチュアがプロの大会で優勝した場合の賞金の行方
- アマチュア資格の取得方法と大会への参加手順
ゴルフ賞金とアマチュア資格の基本

- アマチュアとプロの違い
- アマチュア資格の取得方法
- アマチュア資格を保つメリット
- アマチュア賞金の上限と賞金規定
- アマチュア優勝賞金はどうなる?
アマチュアとプロの違い

ゴルフにおける「アマチュア」と「プロ」の最も根本的な違いは、ゴルフをプレーする目的にあります。
非常にシンプルに言えば、ゴルフを通じて報酬(賞金、レッスン料、スポンサー収入など)を得ることを目的としているか、それとも純粋にスポーツとしての挑戦や自己向上のためにプレーしているかの違いです。
プロゴルファーは、ゴルフを自らの職業とし、生計を立てています。
彼らはトーナメントに出場して高額な賞金を獲得することを目指したり、ゴルフの技術指導(レッスン)を提供して報酬を得たりします。
プロとして認められるためには、通常、日本プロゴルフ協会(PGA)や日本女子プロゴルフ協会(JLPGA)といった統括団体が実施する厳しいプロテストに合格する必要があります。
あるいは、アマチュアの身分のままプロのトーナメントで優勝するという、極めて稀なケースでプロ資格を得ることもあります。
一方、アマチュアゴルファーは、賞金やその他の営利的な目的を持たず、スポーツとしてのゴルフそのものを追求するプレイヤーを指します。
ゴルフを始めたばかりの初心者から、プロに匹敵するほどの高いスキルを持つトップアマチュアまで、そのレベルに関わらず、報酬を目的としていなければ全員がアマチュアゴルファーです。
彼らにとってゴルフは、自己ベストの更新、仲間との交流、あるいは公式なアマチュア競技での名誉をかけた挑戦といった、非金銭的な価値を持つ活動なのです。
ノンアマチュアという存在
少し補足すると、ゴルフ界には「ノンアマチュア」というカテゴリーも存在します。
これは、アマチュア資格規則に縛られずにゴルフを楽しむ人々、例えばアマチュア競技に出場する意思のないゴルファーなどを指します。
ノンアマチュアであれば、プライベートなコンペなどでアマチュア資格規則で定められた上限を超える高額な賞品を受け取っても、規則違反とはなりません。
ただし、ノンアマチュアの身分では、公式なアマチュア競技への参加資格はありません。
もちろん、スキルの面では一般的にプロの方が高いレベルにあります。
プロになるためには厳しいテストをクリアする必要があり、日々の練習量や質、試合経験もアマチュアとは比較になりません。
しかし、近年では中島啓太選手や蟬川泰果選手のように、アマチュアでありながらプロのトーナメントで優勝を飾る選手も登場しており、トップレベルにおいてはスキル面での境界線は必ずしも明確ではなくなってきています。
それでもなお、「報酬を得ることを目的とするか否か」という点が、アマチュアとプロを区別する最も本質的な違いと言えるでしょう。
蟬川泰果選手の活躍はこちらにもまとめてあります。
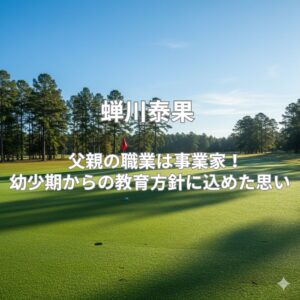
アマチュア資格の取得方法

「アマチュア資格」とは、厳密には特定の試験を受けて取得するような資格ではありません。
むしろ、「アマチュアとして公式な競技に参加するための資格(ステータス)」と理解するのが適切です。
具体的には、ゴルフ規則を統括するR&A(英国ゴルフ協会)とUSGA(全米ゴルフ協会)が定める「アマチュア資格規則」に違反する行為をしていないゴルファーであれば、基本的に誰もがアマチュア資格を有していると見なされます。
しかし、日本アマチュアゴルフ選手権のような公式なアマチュア競技に出場するためには、単に「自分はアマチュアだ」と主張するだけでは不十分です。
多くの場合、自身のゴルフの実力を客観的に証明し、競技を公平に行うための指標が必要となります。
その最も一般的な指標が、「JGA/USGAハンディキャップインデックス」です。
JGA/USGAハンディキャップインデックスの取得プロセス
このハンディキャップインデックスは、日本ゴルフ協会(JGA)が、USGA(全米ゴルフ協会)のシステムを採用して管理・運用している、世界標準のハンディキャップシステムです。
プレーヤーの潜在的な技量を示す数値であり、異なるレベルのゴルファーが公平に競い合えるようにするために用いられます。
取得するには、主に以下の方法があります。
ハンディキャップインデックス取得の主な方法
- JGA加盟ゴルフ倶楽部の会員になる:多くのゴルフ場のメンバーになると、そのクラブを通じてスコアカードを提出し、ハンディキャップを算出・管理してもらえます。最も伝統的な方法です。
- JGA個人会員になる:特定のゴルフ倶楽部に所属していなくても、JGAに年会費を支払い個人会員として登録することで、JGAのシステムを通じてハンディキャップを取得・管理できます。
- JGAが認めるハンディキャップ管理サービスを利用する:近年増えている方法で、日本パブリックゴルフ協会(PGS)加盟コースや、楽天GORA、GDO(ゴルフダイジェスト・オンライン)などが提供するスコア管理システムを利用することでも、JGA/USGAハンディキャップインデックスを取得できます。これらのサービスは、ゴルフ場のメンバーでなくても利用できるため、多くのゴルファーにとって利便性が高まっています。
(参照:JGA公式サイト ワールドハンディキャップシステムについて)
これらの方法で有効なJGA/USGAハンディキャップインデックスを取得し、保持していることが、多くの公式アマチュア競技へのエントリー条件となっています。
取得プロセス自体は、スコアカードを数枚提出することから始まるため、それほど難しいものではありません。
競技出場を目指す方は、まずご自身のハンディキャップインデックスを取得することから始めると良いでしょう。
アマチュア資格を保つメリット

プロゴルファーに匹敵する、あるいはそれ以上の実力を持つトップアマチュア選手の中には、プロ転向の資格を得ても、あえてアマチュア資格を保持し続ける選択をする選手がいます。
それには、アマチュアならではのメリットや、プロという道を選ばない理由が存在します。
アマチュア資格を保持し続ける主なメリットとしては、以下の点が挙げられます。
- 最高峰のアマチュア競技への出場権:「日本アマチュアゴルフ選手権」や「日本女子アマチュアゴルフ選手権」など、各国のゴルフ協会が主催する、歴史と権威のあるアマチュア最高峰のタイトルを目指すことができます。
これらの大会は、プロになると出場資格を失います。また、「オーガスタナショナル女子アマチュア」のように、世界トップクラスのアマチュアだけが招待される特別な大会への出場チャンスもあります。 - プロとは異なるプレッシャー環境:プロゴルファーは、賞金やシード権、スポンサーへの責任など、ゴルフの成績が直接生活や契約に結びつくという、非常に大きなプレッシャーの中で戦っています。
一方、アマチュアは(スポンサー契約が可能になったとはいえ)基本的には金銭的なプレッシャーから解放され、純粋にゴルフの技術向上やコースへの挑戦を楽しむことに集中しやすい環境にあります。 - ゴルフ場メンバーシップ等の権利維持:一部の歴史ある名門ゴルフ倶楽部などでは、会員規約でプロフェッショナルゴルファーのメンバーシップやプレーを制限している場合があります。
アマチュア資格を保持していれば、そうした心配なく、メンバーとしてゴルフを楽しむことができます。
プロになることの現実的な壁
一方で、プロになること自体が極めて困難であるという現実も、アマチュアでいる理由の一つとして無視できません。
前述の通り、プロテストの合格率は非常に低く、毎年多くの有望な選手が涙をのんでいます。
また、プロテストの受験や、プロとしてツアーを転戦するには莫大な費用がかかります。
経済的な負担や、プロとして成功できる保証がない厳しい競争環境を考慮し、学業や他の仕事と両立しながら、アマチュアとしてゴルフを続ける道を選ぶ選手も少なくありません。
アマチュア資格を保持することは、単にプロになれない、あるいはならないというだけでなく、アマチュアならではの名誉やゴルフの楽しみ方を追求するための積極的な選択肢でもあるのです。
アマチュア賞金の上限と賞金規定

ゴルフ界におけるアマチュアリズムの根幹に関わるルールとして、長らくアマチュア選手が賞金を受け取ることは厳しく制限されてきました。
しかし、時代の変化と共にその考え方も見直され、2022年1月1日にアマチュア資格規則が大幅に改定されました。この改定により、アマチュアゴルファーと賞金(および報酬)の関係は大きく変わりました。
賞金受け取りの基本ルール(2022年改定後)
改定後の最も大きなポイントは、アマチュアも一定の条件下で賞金を受け取ることが認められた点です。
ただし、無制限に受け取れるわけではなく、明確な上限額と条件が定められています。
| 競技形式 | 賞金 | 賞品 |
|---|---|---|
| スクラッチ競技 (ハンディキャップを用いない) | 10万円相当額まで受け取り可能 | 10万円相当額まで受け取り可能 |
| ハンディキャップ競技 (新ぺリア方式など) | 受け取り不可 | 10万円相当額まで受け取り可能 |
※賞金・賞品の上限額は、国際基準である700英ポンドまたは1000米ドルを基に、日本では10万円相当額と定められています。
重要なのは、賞金を直接受け取れるのは、スクラッチ競技に限られるという点です。
一般的な企業コンペや友人同士のコンペでよく採用される、ハンディキャップを適用して順位を決める競技形式では、従来通り賞金を受け取ることはできません。
ただし、賞品であれば、その価値が10万円相当額までであれば受け取ることが可能です。
スポンサー契約・広告出演の自由化
もう一つの大きな変更点は、アマチュアゴルファーがスポンサー企業から金銭的な支援を受けることや、広告に出演して報酬を得ることに関する制限が完全に撤廃されたことです。
改定前は、競技にかかる費用の一部支援(上限あり)や、用具の提供(モニター契約)程度しか認められていませんでした。
この変更により、トップアマチュア選手は、プロと同様に企業とスポンサー契約を結び、活動資金を得ることが可能になりました。
すでに、アマチュアでありながら多数の企業と契約し、高額な契約金を得ているとされる選手も登場しています。
これは、才能ある選手が経済的な理由で活動を断念することが減り、より早期から国際的な経験を積む機会が増えるなど、ゴルフ界全体のレベルアップに繋がる可能性を秘めています。
これらの規則に関する詳細は、日本ゴルフ協会(JGA)公式サイトのアマチュア資格規則ページで確認できます。
アマチュア優勝賞金はどうなる?

アマチュア選手が、賞金総額の非常に高いプロのゴルフトーナメントで優勝した場合、その高額な優勝賞金は一体どうなるのでしょうか?
これも、アマチュア資格規則の改定と、それに伴う各統括団体の規定変更により、近年扱いが変わってきている注目のポイントです。
以前の一般的なルール:「繰り下がり」
長年にわたり、ほとんどのプロゴルフツアーで採用されていたのは「繰り下がり」というルールでした。
これは、アマチュア選手が優勝した場合、その選手はアマチュア資格を維持するために優勝賞金を受け取ることができず、その賞金は2位以下の最上位のプロ選手に全額支払われる、というものです。
例えば、記憶に新しいところでは、2022年の「日本オープンゴルフ選手権」で当時アマチュアだった蟬川泰果選手が優勝しましたが、規定により優勝賞金4200万円は受け取れず、単独2位だったプロの比嘉一貴選手がこの賞金を獲得しました。
同様に、2016年の「日本女子オープンゴルフ選手権」でアマチュア優勝した畑岡奈紗選手の優勝賞金2800万円は、2位の堀琴音選手(当時プロ)が手にしています。
現在のJGA主催ナショナルオープンの新ルール:「順位通りの配分」+「上限額支給」
この「繰り下がり」ルールについては、「優勝していない選手が優勝賞金を得るのはおかしいのではないか」「アマチュア選手の功績が正当に評価されていない」といった様々な意見がありました。
これを受けて、日本ゴルフ協会(JGA)は、自らが主催するナショナルオープン(日本オープン、日本女子オープン、日本シニアオープン)において、2025年シーズンから賞金配分に関するルールを変更しました。(参照:JGAニュースリリース 2025年8月13日)
新しいルールは以下のようになります。
JGA主催ナショナルオープンにおけるアマチュア優勝時の賞金配分(2025年~)
- 賞金は、アマチュアを含めた最終順位に基づいて配分表通りに計算される。
- 優勝したアマチュア選手は、アマチュア資格規則で定められた上限額である10万円を受け取る。
- 2位のプロ選手は、配分表通りの正規の2位の賞金額を受け取る。(優勝賞金は受け取れない)
- アマチュア選手が受け取らなかった賞金の差額(例:優勝賞金 – 10万円)は、JGAによってジュニア育成やゴルフ振興などの公益目的事業に活用される。
この変更により、プロ選手にとっては賞金獲得のチャンスが減る一方で、「優勝者が正当に評価される」という競技の公平性がより重視される形となりました。
他のトーナメントが今後このJGAの新ルールに追随するかどうかは、現時点では不明ですが、ゴルフ界全体の流れに影響を与える可能性のある重要な変更と言えるでしょう。
ゴルフ賞金とアマチュアからプロへの道

- プロになるにはどうすればいい?
- アマチュア優勝からのプロ転向
- アマチュア大会に出るには?
- 初心者向けのアマチュア大会
- 変わるゴルフの賞金とアマチュア
プロになるにはどうすればいい?

アマチュアゴルファーが、ゴルフを職業とする「プロゴルファー」になるための道は、大きく分けて2つ存在します。
どちらの道も非常に険しく、卓越した才能と努力、そして多くの場合、経済的な支えが必要となります。
ルート1:プロテストに合格する
最も一般的で正統なルートが、各国のプロゴルフ協会が年に一度実施するプロテスト(クォリファイングトーナメント、Qスクールなどとも呼ばれる)に合格することです。
日本では、男子は日本プロゴルフ協会(PGA)、女子は日本女子プロゴルフ協会(JLPGA)がそれぞれプロテストを管轄しています。
このプロテストは、単にゴルフのスコアが良いだけでは合格できません。
- 複数段階の実技テスト:多くの場合、プレ予選から始まり、1次、2次、最終と、段階的に絞り込まれる厳しい実技テストをクリアする必要があります。各段階で規定のスコアや順位をクリアしなければならず、最終プロテストまで辿り着くこと自体が非常に困難です。
- 筆記試験など:ゴルフ規則やマナーに関する筆記試験、面接などが課される場合もあります。プロとして活動する上で必要な知識や人格も問われます。
- 狭き門:最終プロテストまで進んでも、合格できるのは上位のごく一部(例えばJLPGAでは上位20位タイまでなど)に限られます。年によって多少変動はありますが、全体の合格率はわずか数パーセント(3〜5%程度)という極めて厳しい世界です。
- 高額な費用:各段階のテストには受験料がかかり、会場までの交通費や宿泊費、練習ラウンド費用なども自己負担となります。最終プロテストまで進むと、総額で100万円以上の費用がかかることも珍しくありません。
このように、プロテスト合格は技術、精神力、経済力のすべてが揃って初めて達成できる、非常に高いハードルなのです。
ルート2:アマチュアとしてプロのトーナメントで優勝する
もう一つの道は、アマチュアの身分のまま、推薦などでプロの公式ツアートーナメントに出場し、そこで優勝するというものです。
プロのトーナメントで優勝したアマチュア選手には、通常、そのツアーの複数年間のシード権(出場権)が与えられます。
この権利を得た選手が、プロゴルフ協会に対して「プロ宣言」を行い、所定の手続き(入会申請、入会金の納入など)を経ることで、プロテストを受けることなくプロゴルファーとして登録され、活動を開始できます。
過去には石川遼選手、松山英樹選手、畑岡奈紗選手、古江彩佳選手、蟬川泰果選手など、数々のスター選手がこのルートでプロの世界に入りました。
プロテストという関門をスキップできるため、ある意味「シンデレラストーリー」とも言えますが、トッププロが多数出場する中でアマチュアが優勝すること自体が、歴史的に見ても極めて稀な出来事であり、プロテスト合格以上に困難な道と言えるかもしれません。
どちらのルートを選ぶにしても、プロゴルファーになるためには、幼少期からのたゆまぬ努力と才能、そして周囲のサポートが不可欠であることは間違いありません。
アマチュア優勝からのプロ転向

前述の通り、アマチュア選手がプロのツアートーナメントで優勝することは、プロへの扉を開くための特別なルートとなり得ます。
これは、プロテストという厳しい関門を経ずに、一気にトップツアーで戦う資格を得られる可能性があるため、多くの若手アマチュア選手にとって大きな目標の一つです。
優勝後のプロ転向プロセス
アマチュア選手がプロのレギュラーツアー(JGTOやJLPGAのメインツアー)で優勝した場合、通常、以下のような流れでプロ転向の手続きが進みます。
- 優勝による資格獲得:優勝したことにより、多くの場合、翌シーズン以降の複数年間のシード権(ツアー出場権)を獲得します。
- プロ宣言:選手本人が、プロゴルファーとして活動する意思を表明します(「プロ宣言」)。これは、アマチュア資格を放棄することを意味します。
- 協会への入会申請:所属するプロゴルフ協会(PGAやJLPGA)に対し、正式な入会申請書類を提出します。
- 理事会等の承認:協会内で審査が行われ、入会が承認されます。
- 入会金等の納入:所定の入会金や年会費を納入します。
- プロ登録完了:上記の手続きを経て、正式にプロゴルファーとして登録され、ツアーメンバーとしての活動が可能になります。
例えば、2019年に高校3年生で「富士通レディース」に優勝した古江彩佳選手は、このプロセスを経て、本来受験するはずだった最終プロテストを受けることなく、スムーズにプロの世界へと進みました。
下部ツアー(ステップ・アップ・ツアーなど)での優勝の場合
注意が必要なのは、これが主にレギュラーツアーでの優勝の場合である点です。
女子のステップ・アップ・ツアー(JLPGAの下部ツアー)でアマチュア選手が優勝した場合、得られる特典は通常、レギュラーツアーとは異なります。
多くの場合、プロテストの一部(1次・2次)が免除され、最終プロテストから出場できる権利が付与される、といった内容になります。
しかし、プロテストの受験年齢制限(JLPGAでは17歳以上)などの規定により、優勝してもその特典をすぐに行使できないケースも存在します。(例:2025年に16歳でステップ・アップ・ツアー優勝した後藤あい選手)
アマチュア優勝は、実力を世に示し、プロへの道を一気に切り拓くための強力なパスポートとなり得ますが、どのレベルのツアーで優勝したかによって、その後のプロセスや得られる資格が異なることを理解しておく必要があります。
アマチュア大会に出るには?
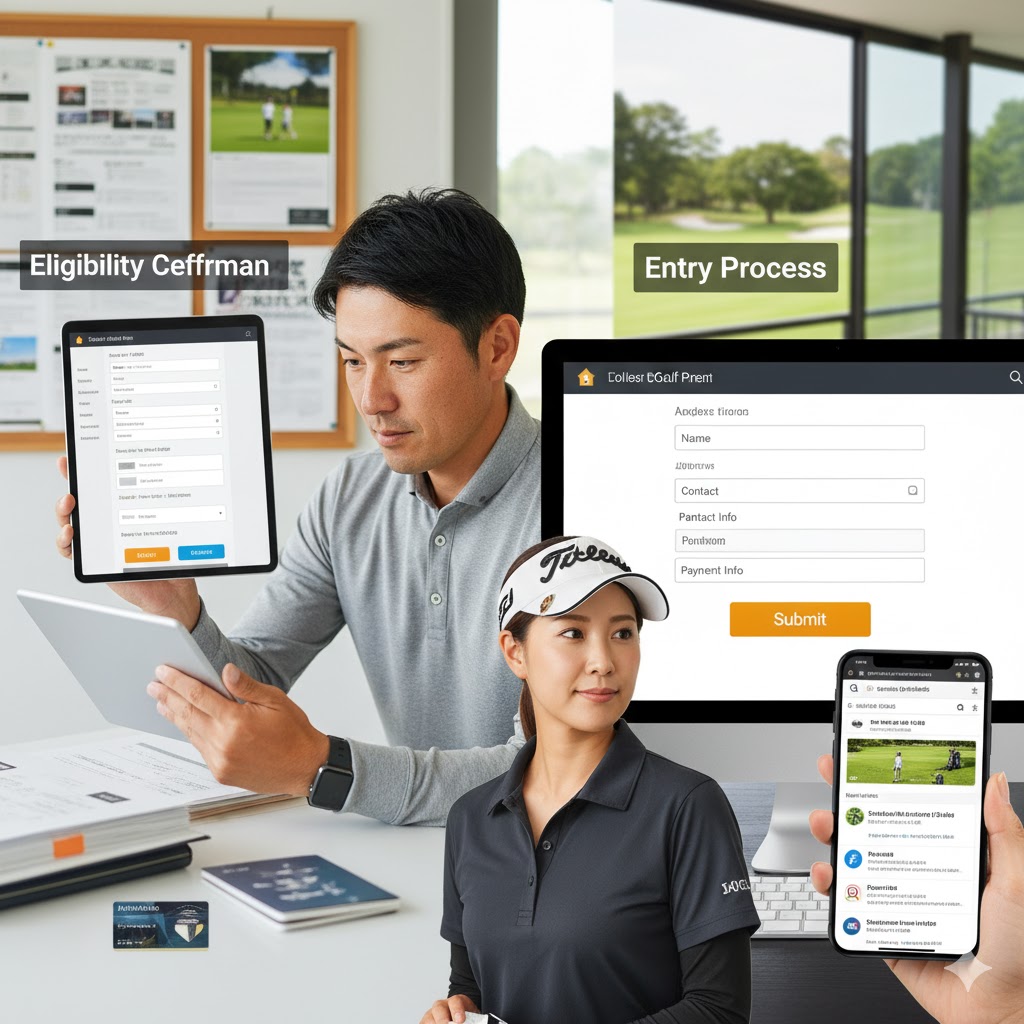
日々の練習の成果を試し、ゴルフの腕をさらに磨くために、「競技ゴルフ」の世界に足を踏み入れたいと考えるアマチュアゴルファーは少なくありません。
仲間内のコンペとは違う、公式ルールに則った真剣勝負の場であるアマチュア大会に出場するには、いくつかの準備と手順が必要です。
1. 参加資格を確認する
まず最も重要なのは、出場したいアマチュア大会の募集要項をしっかりと確認し、自分がその参加資格を満たしているかを確認することです。
大会によって、参加資格は様々です。
| 主な参加資格の項目 | 内容例 |
|---|---|
| ハンディキャップ | JGA/USGAハンディキャップインデックスを保持していること。さらに「〇〇以下」といった上限が設けられている場合が多い(例:日本アマは8.4以下、関東アマは18.0以下など)。ハンディキャップ不要の大会もあります。 |
| 所属 | 特定のゴルフ連盟(関東ゴルフ連盟など)に加盟しているゴルフ倶楽部のメンバーであること、またはJGA個人会員であることなどが条件の場合があります。 |
| 年齢・性別 | ジュニア(例:18歳未満)、ミッドアマ(例:25歳以上)、シニア(例:50歳以上)、女子など、対象者が限定されている場合があります。 |
| 居住地・勤務地 | 都道府県対抗競技など、特定の地域に居住または勤務していることが条件の場合があります。 |
2. エントリー(申し込み)を行う
参加資格を満たしていることが確認できたら、指定された方法でエントリーを行います。
- オンラインエントリー:大会公式サイトや、スポーツエントリーなどの外部エントリーサイトから申し込む形式が主流です。
- 所属クラブ経由:所属しているゴルフ倶楽部を通じて申し込む必要がある大会もあります(特に連盟主催の競技など)。
- 郵送・FAX:一部の大会では、紙のエントリーシートを郵送またはFAXで送付する形式の場合もあります。
エントリー時には、氏名、連絡先、ハンディキャップ情報などの入力・記入が必要です。
また、多くの大会ではエントリーフィ(参加費)の支払いが必要となります(プレーフィは別途当日ゴルフ場に支払うのが一般的です)。
どこで大会情報を探すか?
アマチュア大会の情報は、以下のような場所で探すことができます。
- 日本ゴルフ協会(JGA)や各地区ゴルフ連盟のウェブサイト
- 日本パブリックゴルフ協会(PGS)のウェブサイト
- GDO、楽天GORA、ALBA.Netなどのゴルフポータルサイトの競技・イベント情報ページ
- スポーツエントリーなどのエントリー代行サイト
- 所属しているゴルフ場の掲示板やウェブサイト
まずは、ご自身のレベルや目標(地域で上位を目指したい、全国レベルに挑戦したい、など)に合わせて、出場可能な大会を探してみることから始めましょう。
募集要項をよく読み、不明な点は主催者に問い合わせるなどして、確実にエントリー手続きを進めることが大切です。
初心者向けのアマチュア大会

「競技ゴルフに挑戦してみたいけれど、いきなり公式戦のようなレベルの高い大会は不安…」「ルールやマナーもまだ自信がない」と感じる初心者の方も多いでしょう。
しかし、心配はいりません。近年、ゴルフ初心者でも気軽に参加し、競技ゴルフの雰囲気を楽しみながら学べるアマチュア大会が数多く開催されています。
初心者向け大会が参加しやすい理由
これらの大会は、経験の浅いゴルファーが安心して参加できるよう、様々な工夫が凝らされています。
- 参加資格のハードルが低い:JGA/USGAハンディキャップが不要であったり、スコアによる制限がなかったりする場合が多いです。「ゴルフ歴〇年未満限定」「平均スコア100以上の方歓迎」といった、まさに初心者向けのカテゴリーが設けられていることもあります。
- レベルに応じたクラス分け:参加者を実力に応じてクラス分け(例:Aクラス、Bクラス、エンジョイクラス)することで、同程度のレベルのゴルファーと一緒にプレーできる配慮がされています。これにより、実力差がありすぎて気まずい思いをしたり、プレッシャーを感じすぎたりすることを防げます。
- 多様な競技形式:通常のストロークプレーだけでなく、ペア戦(2人1組)やチーム戦(4人1組など)の形式を採用している大会も人気です。特に、チーム全員の良い方のボールを選択してプレーを進めるスクランブル方式は、個人のミスがチームでカバーできるため、初心者でも気負わずに参加できます。
- ルール説明やサポート体制:競技前に簡単なルール説明会を実施したり、当日の進行をスタッフが丁寧にサポートしてくれたりする大会もあります。ローカルルール(6インチOKなど)を一部採用し、厳格すぎない運営を心掛けている場合もあります。
初心者におすすめの大会・イベント例
具体的に、以下のような大会やイベントが初心者にとって参加しやすいでしょう。
- GDO主催のアマチュアゴルフトーナメント:「GDOエンジョイカップ」など、レベル別・形式別に非常に多くの大会を開催しており、初心者向けのカテゴリーも豊富です。
- Gridge Cup(グリッジカップ):ゴルフ情報サイト「Gridge」が主催するイベントで、”エンジョイゴルフ”をコンセプトにしており、初心者や女性ゴルファーが参加しやすい和やかな雰囲気が特徴です。
- ゴルフ場主催のオープンコンペ:多くのゴルフ場が独自に開催しているコンペティションです。競技性は比較的低いですが、順位付けがあり、賞品も用意されていることが多く、大会の雰囲気を気軽に体験するのに適しています。
- ゴルフスクール主催のラウンドレッスンやコンペ:通っているスクールが主催するイベントであれば、顔見知りのコーチや生徒と一緒に参加できるため、初めてでも安心感があります。
これらの大会は、「競技」という言葉に気負わず、まずは「楽しむこと」「雰囲気に慣れること」を目標に参加してみるのが良いでしょう。
競技ゴルフの第一歩として、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。
変わるゴルフの賞金とアマチュア
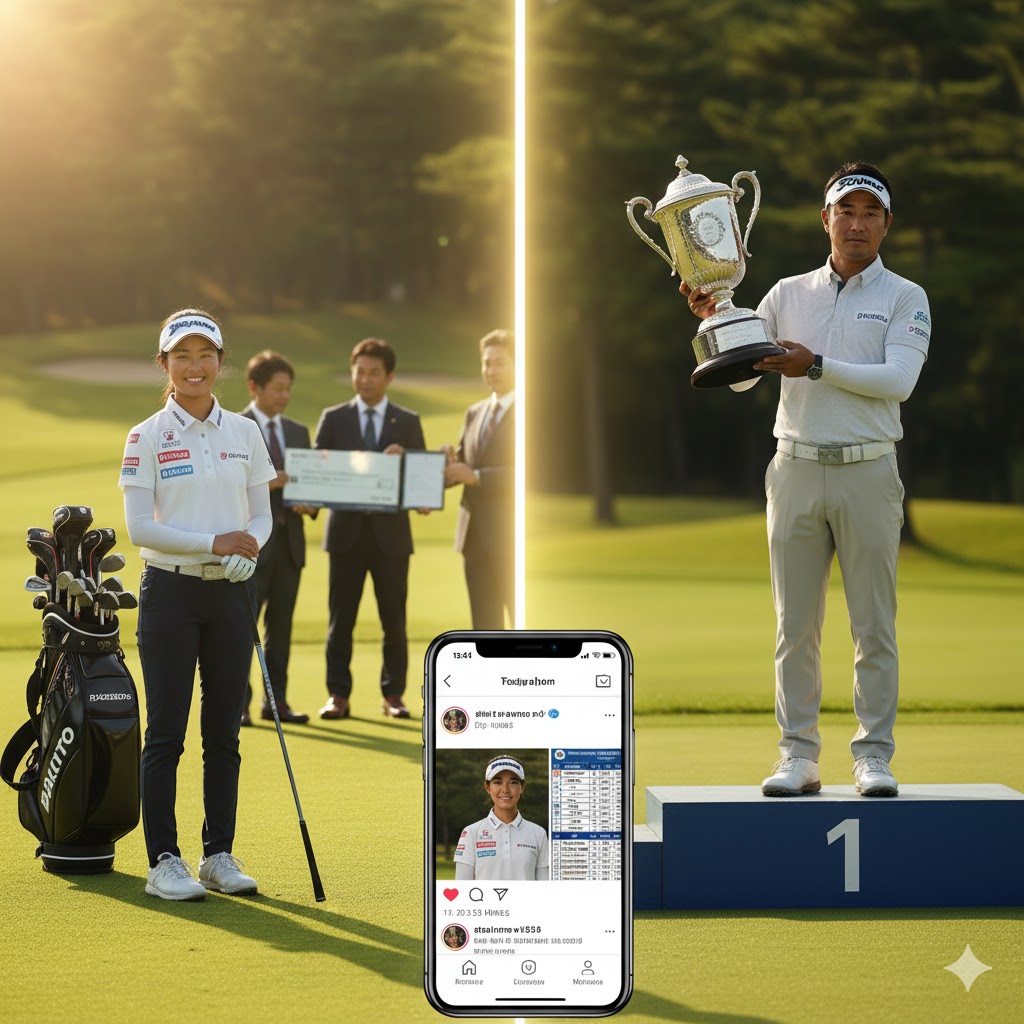
2022年1月1日に施行されたアマチュア資格規則の大幅な改定は、ゴルフ界における「アマチュア」の立ち位置、特に賞金やスポンサーシップとの関わり方に大きな変化をもたらし、そのあり方を問い直すきっかけとなっています。
経済的自立への道と早期育成の可能性
最大のインパクトは、やはりスポンサー契約や広告出演に関する制限が撤廃されたことです。
これにより、才能ある若手アマチュア選手は、プロになる前から企業と契約を結び、活動に必要な資金(遠征費、用具費、コーチング費用など)を得ることが可能になりました。
これは、経済的な理由で競技活動を断念せざるを得なかった選手にとって大きな朗報であり、より多くの選手が早期から国内外のハイレベルな試合経験を積むチャンスを得られることを意味します。
すでに、10社以上の企業と契約し、推定で数億円規模の契約金を得ているとされるジュニア選手(須藤弥勒選手など)も登場しており、アマチュア選手の活動がよりプロフェッショナル化していく流れが加速しています。
これは、選手の早期育成や、ゴルフ界全体のレベル向上、そして新たなスター選手の誕生に繋がるというポジティブな側面を持っています。
アマチュアリズムの定義とプロとの境界線
一方で、この変化は、伝統的な「アマチュアリズム」の概念に一石を投じるものでもあります。
「アマチュアとは、金銭のためではなく、純粋にスポーツの挑戦のためにプレーする者」という従来の定義からすると、多額のスポンサー収入を得て活動する選手を、果たして純粋なアマチュアと呼べるのか?という議論も生まれています。
賞金の受け取りに上限(10万円)が設けられているとはいえ、スポンサー収入に上限がない現状では、一部のトップアマチュアは、多くのプロゴルファーよりも経済的に恵まれた環境で活動できる可能性すらあります。
これにより、プロとアマチュアの境界線は、スキル面だけでなく、経済的な面においても曖昧になりつつあると言えるでしょう。
ゴルフ規則を定めるR&AやUSGAは、「ゴルフというスポーツが現代社会においてどのようにあるべきか」を常に考慮し、規則を改定しています。
今回の変更も、オリンピックでのプロ解禁や、SNSの普及による個人の発信力の増大といった、時代の流れを反映したものと言えます。
今後、この新しいルールがゴルフ界にどのような影響を与え、プロとアマの関係性がどう変化していくのか、引き続き注目していく必要がありそうです。
まとめ:ゴルフ賞金とアマチュアのルール
この記事のポイントをまとめます。
- アマチュアは報酬目的でなく純粋にゴルフを楽しむプレイヤー
- プロはゴルフを職業とし賞金や報酬を得るプレイヤー
- アマチュア資格は規則違反がなければ基本的にゴルファー全員が持つ
- 公式競技参加にはJGA/USGAハンディキャップ取得が一般的
- アマチュア資格のメリットはアマ競技出場権やプレッシャーの少なさ
- 2022年規則改定でアマチュアも賞金受け取りが可能に
- 賞金受け取りはスクラッチ競技で上限10万円相当額まで
- ハンディキャップ競技では賞金不可(賞品は10万円相当まで可)
- アマチュアのスポンサー契約や広告出演の制限は撤廃された
- プロ大会でアマが優勝した場合、以前は賞金全額がプロへ繰り下げ
- JGA主催ナショナルオープンでは優勝アマは10万円、2位プロは2位賞金に
- アマが受け取らない賞金差額はJGAの公益事業に活用される
- プロになる道は主にプロテスト合格かアマチュアでのツアー優勝
- プロテストの合格率は3-5%と非常に狭き門
- アマチュア大会参加には資格確認とエントリーが必要
- 初心者でも参加しやすいハンデ不問やチーム戦の大会も多数ある